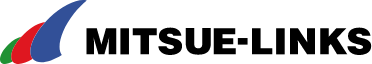日本視覚障害者ICTネットワークが第4回支援技術利用状況調査報告書を公開
アクセシビリティ・エンジニア 大塚日本視覚障害者ICTネットワークが、4回目となる支援技術利用状況調査の報告書を公開しました。2023年に行われた第3回の調査結果と比較しながら、個人的に印象に残った点を取り上げます。
まず、パソコンで使うことのある支援技術に関連した質問では、全体的な回答の傾向に極端な変化はなく、PC-Talkerの利用率の高さが目立っています。一方、使用することのある支援技術を複数選択する設問では、NVDAを挙げる回答者が6割に迫っており、NVDAの利用率が伸び続けていることがわかります。
また、利用することの多いスクリーンリーダーの組み合わせを前回調査と比較すると、PC-Talkerといずれかのスクリーンリーダーの組み合わせを選ぶ回答者が減少しており、主に利用する支援技術を1つ選ぶ質問ではNVDAの割合が増加していました。そのため、スクリーンリーダーの利用頻度にかかわらず、NVDAの利用者が増えていることが考えられます。特に若年層でNVDAの利用率が高く、年齢が上がるにつれてPC-Talkerの利用率が高まる点にも注目したいです。
パソコンで利用しているWebブラウザについては、NetReaderの利用率が下がり、Google ChromeやFirefoxの利用率がやや増加しており、スクリーンリーダーの利用率を反映した形となっていました。わずかではあるものの、Internet Explorer(IE)の利用があった点も興味深く、一部では古いOSやスクリーンリーダーが利用し続けられている現状があることが推測されます。
スマートフォンの利用に目を向けると、全盲でiOSとAndroidを組み合わせて利用する回答者が増えており、これはAndroidに搭載されているTalkBackの一部のジェスチャーが、VoiceOverに近いものへと変更されつつあることも影響していると考えられます。40代から50代にかけてAndroidを組み合わせている利用者数が増えている点も興味深いです。
今年の調査では、文字認識や画像認識についての質問もあり、認識機能を使って確認するものとして、書籍を選択した回答者が28.71%と思いのほか多く、驚きました。文字認識では、レイアウト通りの順序で読み上げなかったり、正しく文字が認識されないこともあるため、どのように書籍の読み上げに活用しているのかが気になりました。
調査結果全体の印象はおおむね予想通りでしたが、わずかながらIEの利用者が存在した点や、思いのほか書籍で文字認識が利用されていた点など、予想外の内容もありました。また、これまで漠然としたイメージで捉えていた年齢ごとの支援技術の利用状況が判明し、回答者の年齢に注目する必要性を再認識しました。調査結果の詳細については、第4回支援技術利用状況調査報告書 | 日本視覚障害者ICTネットワークからぜひご覧ください。