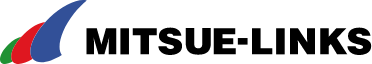Webアクセシビリティ向上におけるチェックツール活用の意義
エグゼクティブ・フェロー 木達 一仁Web全体をグローバルに捉えたとき、果たしてコンテンツのアクセシビリティは年々、改善傾向にあるのでしょうか?残念ながら、The WebAIM Millionにある調査結果や、The 2024 Web AlmanacのChapter 8: Accessibilityを眺める限り、そうは思えません。
まったく改善が進んでいない、というわけではありません。しかし、Webアクセシビリティ向上のための知識・技術が以前より広く普及し、また多くの国・地域でアクセシビリティへの取り組みが法制化されつつある割に、改善の進捗はかんばしくない印象を受けます。
経済や社会が変化のスピードを増すなか、多くのWebサイトで、コンテンツを追加ないし更新するワークフローに、アクセシビリティを確保するためのプロセスが、しっかり組み込まれていないのだろうと察します。真実そうだったとして、どうすればその状況から脱却できるでしょう?
さまざまな打ち手が考えられますが、チェックツールの活用が鍵になると私は考えます。
Webコンテンツのアクセシビリティは、その良しあしについて、専門家による目視/手動の検証を必要とするものと、チェックツールと呼ばれるソフトウェアで機械的に検証できるものに大別されます。AI技術が進化しているとはいえ、Webアクセシビリティのすべてを自動で検証することは、現時点では不可能です。
WCAGへの適合やJIS規格への準拠を目標に掲げているなら、目視/手動の検証は欠かせません。しかし、その種の検証を行うには、どうしても一定の時間やコストが必要になりがちです。生身の人間が検証する以上、おのずとその処理能力には限界があるためです。
いっぽう、白黒つけることのできる範囲が限定的とはいえ、人間と異なり疲れを知らないチェックツールは、大量のコンテンツを高速に検証できます。日々コンテンツが増えたり書き換えられたりするWebサイトにおいて、チェックツールに頼らない手はありません。
両者の長所・短所を踏まえるなら、目視/手動の検証を行うより先に、機械で容易に検知できるレベルの問題点をゼロに近づけ「モグラたたき」状態を回避するよう、チェックツールを日常的に活用すべきでしょう。WCAGへの適合なりJIS規格への準拠を目指すのは、そのあとからでも遅くないはずです。
チェックツールには、さまざまな種類の製品があり、無償で使えるものとそうでないもの、UIが日本語化されているものや英語でしか利用できないものなどがあります。以下に、ごく一部を列挙します:
チェックツールで検証可能なWebアクセシビリティは、そうでないものを含めた全体の20~30%しかカバーできないというのが通説ですが、axeやaxe Monitorの開発元であるDeque Systems社は、より高い割合をカバーできるとしています(Dequeが主張する自動アクセシビリティチェックのカバレッジ参照)。
そういうわけで、もしまだチェックツールを活用されていないようであれば、機械的に判別可能なWebアクセシビリティ上の問題点の継続的な削減に、取り組んでいただけたら幸いです。
また、当社でご提供中の2種類あるWebアクセシビリティ診断のうち、「クイック診断」はチェックツールによる機械的な検証に相当し、安価かつ短期間でレポートのご納品が可能です。ぜひご検討ください。
Newsletter
メールニュースでは、本サイトの更新情報や業界動向などをお伝えしています。ぜひご購読ください。