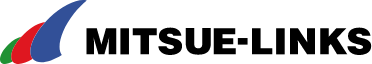改正障害者差別解消法の施行から1年
エグゼクティブ・フェロー 木達 一仁今日は4月1日。多くの組織において新年度が始まる節目のタイミングですが、タイトルにありますように、昨年の4月1日に改正障害者差別解消法(以下「改正法」)が施行されてから、ちょうど1年になります。
改正法については、たびたびコラムで取り上げてきましたので、読者の皆様のなかには、すでに聞き飽きたとお感じの方がいらっしゃるかもしれません(が、本コラムも最後までお付き合いいただけたら幸いです)。
- 障害者差別解消法の改正とWebアクセシビリティ(2021年8月6日)
- 続・障害者差別解消法の改正とWebアクセシビリティ(2023年3月24日)
- 2024年はアクセシビリティに取り組む好機(2024年1月12日)
- 再確認しておきたい改正障害者差別解消法の要点(2024年12月6日)
私の認識する限り、日本国内のWebサイトにおいて、この1年間でどれだけアクセシビリティ品質が高まったかの定量的な調査結果は、存在しません。そこで、実際のWebサイトのアクセシビリティと相関が薄いのは承知のうえで、Google トレンドの「web アクセシビリティ」で過去12カ月の人気度の動向を見てみました。
グラフを見ますと、2024年5〜6月のピークと比べ、この半年近くは概ね半分程度の人気度となっています。これは、当社に寄せられるアクセシビリティ関連の相談件数の傾向と似ており、昨年の春〜夏を過ぎてからは(理由はさておき)件数は落ち着いています。
また、私はウェブアクセシビリティ基盤委員会での活動の一環として、アクセシビリティ方針やJIS X 8341-3に基づく試験結果をSNSで紹介しています。そのためのGoogle アラートを用いた簡易調査を通じても、改正法の施行前と比べ、Webアクセシビリティ向上への取り組みが増えたとは感じません。
従い、個人的かつ主観的な感想ではありますが、施行を機に日本のWebアクセシビリティが明確に前進したとの印象を、私は抱けていません。改正法の施行が日本のWebアクセシビリティを前進させる要因たり得ず、むしろ一過性のトレンドとしてアクセシビリティが捉えられがちと仮定するならば、その原因は何でしょうか?
さまざまな仮説を立てることが可能でしょうが、私のなかで最有力の仮説は、Webアクセシビリティが障害者や高齢者のためだけに求められるという誤解が、いまだ業界ないし社会にはびこっているからです。
確かに、障害者や高齢者は(Webに限らず)アクセシビリティを必要としますし、Webサイトがアクセシブルになることで恩恵を得やすいのは、障害者や高齢者とも思います。しかし、それ以外の人々がアクセシビリティ向上の恩恵に与らないかといえば、完全に誤りです。
ユーザーの年齢や障害の有無にかかわらず、そしてユーザーが用いるハードウェア(PC、スマートフォン、タブレット etc.)やソフトウェア(OS、Webブラウザ etc.)にもかかわらずアクセスできてこそWebであって、そのためにはコンテンツのアクセシビリティ品質が不可欠との基本的な理解を、まだまだ啓発し続ける必要があると私は思います。
とりとめがなくなってきたところで、最後にセミナーの宣伝を。この4月から6月にかけて、Webアクセシビリティに関するオンラインセミナーを3カ月連続で開催(再演)します。いずれも基本的な、これからWebアクセシビリティについて学びたい、取り組みたいとお考えの方にうってつけのセミナーです。
- 4月16日(水)開催:Webアクセシビリティ入門セミナー 2025
- 5月27日(火)開催:画像の代替テキストを考えよう
- 6月5日(木)開催:スクリーン・リーダーで学ぶWebアクセシビリティ
ご多忙中と存じますが、皆様のご参加を心よりお待ちしております。
Newsletter
メールニュースでは、本サイトの更新情報や業界動向などをお伝えしています。ぜひご購読ください。